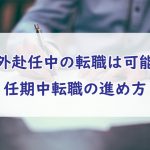コロナ禍によりテレワークは働き方の一つとして一気に浸透しました。
企業によっては「テレワーク完全移行」や「原則的にテレワーク」など、大胆な判断を下したケースもあります。
極端な例ですが筆者の知る企業ではオフィスを完全撤廃し、完全テレワークに以降しました。オフィスは書類を置くだけの場所となり、従業員は出社する必要はありません。
ワーケーションは一時的なものではなく、パンデミックが落ちついた後も続くものと思われます。
このような背景を受けて、一部のワーカーは「ワーケーション」を選択しています。
- ワーケーションとは何か?
- 実際に体験した人はどう感じたか?
本記事で上記2つについてお伝えします。
この記事の目次
ワーケーションって何?

ワーケーションとは「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた現代語です。
一言にすると「観光を楽しみながら働く」ということ。
観光地やリゾート地に一定期間滞在しながら、テレワークで仕事もしてしまう、というライフスタイルを意味します。
なぜワーケーションが広まっているのか?
きっかけはパンデミックですが、労働者側と観光地側の両サイドでの変化があります。
労働者側の変化
記事冒頭でお伝えした通り、労働者側では差はあれども多かれ少なかれテレワークが可能となりました。
柔軟性の高い企業では「原則出社」から「原則テレワーク」に切り替えたケースもあります。
人によっては、完全に場に縛られない働き方が可能になったということです。
観光地側の変化
一方の観光地ではパンデミックの影響で観光収入が途絶えてしまいました。
例えば筆者が住むインドネシアには「バリ」という東南アジア屈指の観光地がありますが、コロナ発生以降、外国人観光客は物理的に訪れることができなくなりました。
非常に観光依存度の高いエリアであり、多くの住民が苦しい生活を強いられています。
そのため、観光地やリゾート地は「新しい需要」を作る必要に迫られています。そのうちの一つが「ワーケーション」というわけです。
ワーケーションは通常の観光客よりも収益性は下がるかもしれません。しかし既存の資産をそのまま活用できるのでやらない手はない、といったところでしょう。
実際に体験した人の話を聞いてみた

参考になるかと思い、実際にバリで最近ワーケーションをした方に話を聞かせてもらいました。匿名を希望されているのでイニシャルのみ表示します。
[chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]簡単に現在の就労環境を教えてください[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]外資系メーカー勤務で駐在員としてジャカルタに赴任しています。基本的に自由度の高い職場で、現在は完全にWFH(Work From Home / 在宅勤務)に移行しています。今のところはそれで業務が回っているので、今後も続くかもしれません。[/chat] [chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]どちらでワーケーションをされていたのですか?[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]年始休暇の勢いのまま、2週間ほどバリに滞在していました。[/chat] [chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]なぜワーケーションをしてみようと思ったのですか?[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]どうせ在宅勤務なので、ネットさえあればどこで働いていても同じだな、と思ったからです。それに、コロナの影響で観光地のホテル代が値崩れしてたのも大きいです。バリでも今なら3千円や4千円出せばかなりよいホテルに泊まることができますよ。[/chat] [chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]実施にワーケーションされてみていかがでしたか?[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]とても良い気分転換になりました。朝起きてビーチの前でパソコンを開き仕事をするのは何とも言えない体験です。自宅で仕事をするよりメリハリもつけやすかったかもしれません。残念ながら街の半分ほどは閉じた状態だったのですが、それでも仕事後や週末は小旅行も楽しめました。[/chat] [chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]逆に大変だったことはありましたか?[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]これはバリだからかもしれませんが、たまにネットが弱い日があるのが難点ですかね。自宅であればやりようはあるのですが、旅先なので対応できずでした。あとは特に大変だったことはないですね。[/chat] [chat face=”square_logo_600.jpg” name=”筆者” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]このお話を記事にさせていただく予定なのですが、読んでいる方に向けてメッセージはありますか?[/chat] [chat face=”man1″ name=”MTさん” align=”left” border=”green” bg=”none” style=””]もし現在在宅勤務中心の生活になっているのであれば、ぜひ一度ワーケーションを体験してみてください。1週間や2週間の長期でなくとも、休日を拡張する形で数日間でも十分楽しめると思います。気分もリフレッシュできますし観光経済に貢献できます。逆に2週間以上になると飽きてくるのでご注意ください。何事もバランスですね。[/chat]
まとめ
今回はバリのケースをご紹介しましたが、日本でも沖縄や北海道にショートステイをしながら仕事をする人が出てきているようです。沖縄の離島に1週間ほど滞在して、仕事をするのも素敵ですね。
JALでもワーケーションに便利なパッケージを販売しているのでのぞいてみてください。
観光地の新たな収益源としても、ワーケーションが一つの産業として成長することを期待しましょう。
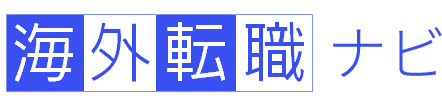









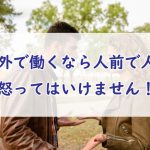

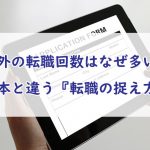
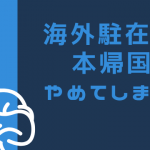

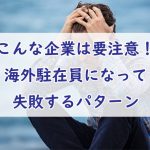

-150x150.jpg)